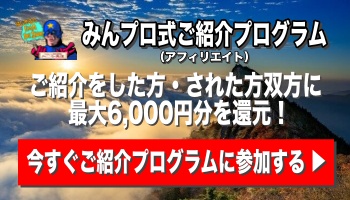Androidアプリを作るためのプログラミング言語であるKotlinとかJavaに限らず、色んなプログラミング言語もそうなんですけれど、そういうものは、他の人の作ったもの(専門用語的には「クラス」と言います)を、勝手に使って自分で新しいものを作ることが許されている。
これを専門用語で「継承」と言ったりしますけど、これが出来るのがプログラミングの世界なんですね。
これはよく考えたらすごいことでありまして、今なんかは、著作権がどうだこうだとかってやってますよね。どっかの音楽教室で子供に教えるためだけに使った曲に対して「著作権料払えや」なんてことを言うような時代になっているわけです。
そんな時代の中で、プログラミングというのは「いやいや、ぼくの作ったものはあなた勝手に使って新しいもの作ったらええやん」というのがまかり通る世界なんですよ。
「他人の作ったアイデアを積極的に使って新しいものを産み出す」ということを、むしろ推奨してるんです。「パクってええよ」と。これがプログラミングの根底に流れている世界観なんですね。
これ大げさな言い方をするとですね、今の世の中なんかは殺伐としてますよね、人間関係が。「周りはみんな敵や」と、競争、競争で。
プログラミングはまさにそれと真逆。無償の助け合いの精神で成り立ってるわけですよ。これはほんまにすごいなという風に思うわけですね。
ですから、これから2020年からプログラミング必修化、小学生からプログラミングやっていくという話が出てきてますよね。
あと大人の方でも、AI(人工知能)の時代やから、英語みたいな感じで「プログラミングっていうのは現代に必須スキルなんや~!」みたいなムーブメントが出てきたりしています。
それはそれで大事なんですが、それだけじゃなくって、プログラミングの根底に流れている「助け合いの世界観」というメンタリティの部分も非常に大切ではないかと。
こういう時代にプログラミングというのが脚光を浴びてきたっていうのは、技術的な話もあるんですけれど、ちょっと怪しい話になりますが、メンタリティ的なところの部分っていうのが、非常に大きくあるんじゃないかなと思ったりしておりまして。
ですから、こうやってプログラミングの技術をお伝えさせて頂く「端くれ」としてですね、技術はもちろん大事だけれども、技術を使うためのメンタリティの方をお伝えする方が大事だということですよね。
アインシュタインの話じゃありませんけれども、原子力を作ったけれども、それを原子力発電、発電も今となってはよかったかどうかわかりませんが、少なくとも電気を作ることに使えば人の役には立つ。
けれど、それで原爆を作ったらとんでもないことになると。でも、それをやったのは、原子力を作ったアインシュタインが悪いわけではなくて、それを使った人間のせいですわということですよね。
ですから、どんなに便利な道具を作ったとしても、それを使う人間の方がしっかりとしたメンタリティを持っておかないと、またとんでもないことになってしまうというのが、これまでの歴史の教訓で、プログラミングに関しても同じことが言えると思うんですよね。
せっかくプログラミングというものが脚光を浴びてきているといった時に、我々のようにこういう技術をお伝えさせて頂く「端くれ」としては、お伝えするべきなのはプログラミングの「技術」だけではなくて、やっぱりそこの根底にある「助け合いの世界観」ではないかと。
もちろん、我々も偉そうなことなんか言えませんけれども、率先してですね、こういう「助け合いの世界観」というものをお伝えしていって、それが世の中に広まっていけば、本当に住みやすい世の中になると思うんですよね。
ですから、そういうことを通じて、未来に希望の持てる明るい世の中の実現に、微力ではありますけれども貢献していきたいと思っているわけであります。